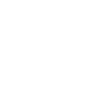イベント・社会連携
HOME > イベント・社会連携 > その他の事業:オリンピック関連事業
東京2020オリンピック競技大会を振り返る講演会
2021年12月2日(木)に、「東京オリンピックのレガシーとは?」をテーマに、東京2020オリンピック競技大会を振り返る講演会を開催いたしました。
講演会には、元NHKエグゼクティブアナウンサーで、30年以上オリンピック大会やW杯などの現場に立ち会い、スポーツ実況を数多く手掛けられ、現在は法政大学スポーツ健康学部教授としてスポーツジャーナリズム論等の授業を担当されている山本浩氏を講師としてお招きするとともに、オリンピアンである本学教員2名、今回の五輪出場選手2名にもご講演いただきました。
山本浩先生(法政大学)

~ハードにソフトに~
<五輪開催地にとってのレガシー>
国際オリンピック委員会(以下:IOC)が「レガシー(LEGACY・遺産)」という用語を積極的にしかも大々的に謳い上げるようになったのは、2014年「アジェンダ(AGENDA・行動指針)」を発表してからです。例えば「持続するレガシーを残すため」「世界的な文化の担い手とダイナミックなレガシーを作り上げる」あるいは「持続可能性とレガシーに強い焦点を当てる」と次々にレガシーが登場しました。
この行動指針を発表した背景には、オリンピック(以下:五輪)大会開催に立候補しようとした都市が「撤退表明」をしたり、招致活動の中で不祥事が起こったり、とてつもない負担に開催をためらったりする声が世界に渦巻くようになったからです。
五輪大会が開催されたあとで、開催都市は報告書を書き上げIOCに提出することが義務づけられています。かつての報告書に書かれた「レガシー」はずっと、施設の意味で使われてきました。1908年第4回ロンドン五輪では、「1896年第1回アテネ五輪の際に『ザッペイオン』という建物が建てられてフェンシング会場として用いられた」と記載され、これに「レガシー」ということばを当てています。その後「レガシー」という表現はしばらく見当たりません。再び登場するのは第二次大戦終了直後の1948年第14回ロンドン五輪です。第二次大戦の空襲を受けて建物があちこちで破壊され、ボクシング会場が不足したためスイミングプール上に橋を渡してリングを設置した際に「プールという『レガシー』があったから実施できた」という報告になっています。1964年第18回東京五輪の報告書では「レガシー」という用語は見当たりません。その後も、開催地の文明や開会式などのセレモニーで行われたアフリカのダンスをそれぞれの国や地域の「レガシー」と紹介している程度です。
「レガシー」という語が報告書に数多く示されるのは、1976年モントリオール五輪です。施設の工事中のストライキや建造物にかかる経費の高騰などから、当初の予算1億2千万カナダドルが16億カナダドルに膨れ上がり、返済に30年かかりました。この大会後、モントリオール組織委員会会長は「建築と偉大な技術、それに文化功績をレガシーとするだけでなく、スポーツの価値を気づかせる」と指摘、現代にも繋がる内容を報告書に載せています。
その後、レガシーを華々しく書き連ねたのは1984年第23回ロサンゼルス五輪です。政府からの援助なしに大会を成功させたことはよく知られています。戦前1932年ロサンゼルス大会の施設を一部利用しながら、企業からの援助を受けて、例えば自転車競技場を大学構内に建設しました。結果的に2億1500万米ドルの黒字を達成したからでしょうか、報告書には「レガシー」ということばが45箇所も記され、大会後に書かれた文言が振るっています。「黒字だけで成功と言ってはいけない。イベントを超えるインパクトを与えた」とした上で、「魅力あふれる2週間が街をひとつにし、皆に喜びと興奮を与えた」とスポーツの持つ力の大きさを訴えました。
その後の報告書に見る「レガシー」という用語は、1988年ソウル9箇所、1992年バルセロナ5箇所、1996年アトランタ60箇所、2000年シドニー45箇所、2004年アテネ31箇所、2012年ロンドン46箇所と頻繁に登場します。一方、2016年リオ大会は、考えられないことですがいまだに報告書は出されていません。
<国際オリンピック委員会にとってのレガシー>
現在の五輪憲章には「オリンピック競技大会の有益な『レガシー』を、開催国と開催都市が引き継ぐよう奨励する」と書かれており、レガシーを考慮して大会を遂行することが五輪開催都市への要望事項となっています。
開催する側だけがレガシーを残せばよいのか。開催都市を決定し五輪を主催するIOCの「レガシーとは何か」を考える必要はないのでしょうか。大会の7年前に開催都市を決定し、さまざまなアドバイスを与えながらIOCは、大会が終わればその国を離れてしまいます。競技場もアリーナもIOCの所有物ではないのです。ではIOCに残るものは何なのでしょう。それは実は「映像」なのです。
私たちがスマートフォンやテレビの画面で目にしたさまざまな競技映像。この映像を制作しているのは、 IOCが2001年に設立した「OLYMPIC BROADCASTING SERVICES(OBS、オリンピック放送機構)」という組織です。
大会の映像制作に当たっては、1994年に設立されたEVSというベルギーの企業のノウハウがあらゆる所に使われています。EVSの技術は、ライブの映像の間に挟まれる短くて鮮明なスローモーションの連続に典型的に見ることができます。

EVS社のコントローラー
IOCの子会社OBSは、夏冬の五輪とパラリンピックでそれぞれ膨大な量の映像を作るのですが、必要な社員をすべて抱えているわけではありません。大会ごとに世界中の放送局や独立プロダクションに声をかけ、優秀な人材を集めて映像制作を依頼しています。OBSができるまでは長い間、開催国の放送機関にほとんどお任せの中継映像作りでした。どこで大会をやっても映像担当者は、ほとんどがオリンピック放送は初めて。開催国で放送したことがない競技が行われると、カメラのセッティング場所も見よう見まねですし、競技の鍵となるシーンを選ぶことに苦労するのは目に見えていました。何とか本番の2週間に及ぶ実践を経て、要領が飲み込めたとしても、次の五輪ではもうその経験が生きないのです。映像のレベルを上げるのに、現場の担当者がコロコロ変わるようでは実現不可能だ。IOCが独自の組織を作ろうと考えたのには、それなりの理由があったのです。
今では、3分間のハイライトシーンも、競技終了後30分以内に五輪の放送権を持っている放送機関へ流せるよう用意しなければなりません。競技やレースはもとより、試合前の監督インタビュー、試合後の選手の声、街の紹介などありとあらゆる映像を、PCやスマートフォンなどで「いつでも、どこでも」見ることができるようにカスタマイズしておく必要があるのです。IOC自身が五輪の映像制作に精通した人間を集めて会社を作り、その会社が世界で名うてのテレビ屋に声をかけて、経験に基づいた安定した映像を作る。放送権料が高すぎるという放送権者の不満に応えるために、レベルの高いサービスを多岐にわたってする必要に迫られての組織替えでした。
IOCの「レガシー」である映像について、もう少し考えてみましょう。五輪を見たいとなると、特に今回のような無観客での大会では、画面での観戦が中心でしょう。この放送(通信)映像を高いレベルで制作しているのは、先述のOBSです。OBSはいわば五輪の公式映像を作るグループ。世界のどの国も基本的にはOBSが作った国際映像を見せられています。万国共通の映像に、それぞれの国のアナウンサーがその国のことばで実況音声を付けているに過ぎません。

OBSの依頼により、中国から運ばれた中継車(相当数のカメラのケーブルの接続が可能)
1964年東京大会の頃から始まって、五輪映像にはさまざまなスローモーション技術が使われてきました。といってもスローモーションが出るのは、限られた時間内に限られた回数でした。ビデオテープを使っていた為に巻き戻してからしか再生できない構造上のハンディーがあったのです。当時の映像を、体操を例に取って想像してみましょう。以前のテレビ放送では「競技場内の雰囲気→選手の顔→演技やプレー→終了後の選手の顔→スローモーション→競技結果」というパターンでした。ところが現在では、先のEVS社の再生システムを駆使して「競技場の雰囲気→選手の顔→演技やプレー→様々なカメラで撮った短めの連続スロー(この時に、関係する周囲の映像を同時進行のような形式で加える)+終了後の選手の顔+競技結果」というようになっています。一つの種目で最低16台といわれる多くのカメラで撮影した映像を組み合わせることで、臨場感豊かな映像を作成しています。
放映権を持つ放送局は、お金を払って独自にカメラを会場内に入れる権利を手にすることができます。放映権を持つ国から出場している選手や監督を中心に撮影するのが目的で、ユニカメラと言ってこれだけは依頼した放送局のカメラマンが操作します。ユニカメラがどのように使われるのか、一つの例をサッカーのシュートシーンで考えてみましょう。日本がメキシコと対戦する試合、日本のFWがシュートをしたが惜しくも外れた場面があったとします。OBSが制作する国際映像では、『シュートをする選手→ゴールを外れるボール→顔を覆うシュートをした選手→シュートを防いだ相手チームのディフェンダーを讃えるチームメイト→スロー再生→相手チームのゴールキック』という流れでしょうか。ここに例えば日本の放送局のユニカメラが入っていれば、『シュートをする選手→ゴールを外れるボール→顔を覆うシュートをした選手→シュートが外れた瞬間に悔しがる森保監督→スロー再生→相手チームのゴールキック』というように、日本の視聴者が共感するような映像構成へと変わります。
映像のきめの細かさは、カメラのセッティングからも類推することができます。陸上競技トラック種目であれば、フィニッシュエリアの延長上にOBSが3台のカメラを設置してスローモーションのためだけに正面から撮影していたのを知っているでしょうか。ファイナリストのうち記録の良い3人をそれぞれが一人ずつ捉えて、レース直後の再生に備えるのです。男子100mの決勝レースではこのカメラゾーンにさらに自国の選手を撮影するユニカメラが7台、ニュース用のカメラが別途設置されていました。競技を伝えるために全てのカメラを合計するとOBSだけで36台もあったのです。

表彰式(女子体操競技 種目別ゆか-銅メダル:村上 茉愛)でのOBSによるカメラ撮影
一つひとつのカメラが4K仕様。ありとあらゆる映像が撮られ、世界中に配信され、印象深いシーンが地球上を駆け巡る。そのすべてに対して権利を持ち、これを未来永劫持ち続けることのできるのはただ一人IOCだけなのです。
「放送局も映像を撮っているはずだ」。
確かに映像そのものはそれぞれの放送局のアーカイブスにしまい込まれるでしょう。しかしそれをいったん放送に載せようとするといきなり、高額な料金が発生してきます。過去のシーンを放送するとなると、秒単位で決められた単価を放送秒分、きっちりと支払わなければなりません。儲かる一方のうまい商売だと見えなくもありませんが、経済的に恵まれない国の子どもたちや、戦争や国内の紛争などでトレーニングのできない選手に、IOCが様々な資金提供を行っているのも事実です。
ク-ベルタンが提唱したIOCのスローガンである「より早く、より高く、より強く」に、今回の五輪では「共に」が加わりました。IOCの「レガシー」、映像が後の世に再現されたときにも「共に」が世界に具現化されることを強く願わずにはいられません。
溝口紀子先生(日本女子体育大学)

東京オリンピックとジェンダー平等
皆さん、こんにちは。本日は当事者として参加した東京オリンピック、そして私の専門である社会学から見た東京オリンピックについてお話ししたいと思います。
まず、当事者として参加した東京オリンピックについてです。フランスオリンピック委員会の強化委員長は私の元同僚であったこと、そして私が住んでいる静岡市がフランスのカンヌ市と姉妹都市であったことが縁で、フランスのテコンドーチームは静岡市でキャンプをすることとなり、私もスタッフとしてキャンプに参加しました。

キャンプ地はサッカーのナショナルトレーニングセンターですが、そこでは朝のPCR 検査や一人一部屋での生活など様々な感染対策がとられ、感染者が出た時点でオリンピックに参加できないという緊張感の中で生活をしていました。バブル方式のキャンプですので、キャンプ地から自由に外出もできません。こうした隔離生活の中で、静岡市の小学校の児童たちがフランスチームへのメッセージカードを作ってくれまして、そのカードはカーテンにしてキャンプ地に飾られました。直接の交流はできませんでしたが、ホストタウンの児童とフランスチームの交流も、オリンピックのレガシーの一つであると思います。
次に、東京オリンピックとジェンダー平等についてです。今回のオリンピックの「レガシー」の一つは「ジェンダー平等」であると思います。オリンピック開催前に当時の組織委員会会長のジェンダー平等に反する発言に端を発して、会長が辞任する問題が起こりました。この問題に関して海外からの取材で「オリンピックが目指すジェンダー平等を実現しなければならない人物がなぜこのような発言をするのか」と尋ねられました。その際に説明したのが日本のスポーツ界の体制です。問題発生時の組織委員会の理事30人のうち女性は7人、評議員6人うち女性はただ1人です。スポーツ団体の役員に女性があまり登用されていない状況が明らかとなりました。
1964年の東京オリンピックでは女子選手の参加は678人でしたが、今回の東京オリンピックでは過去最高となる5176人の女子選手が参加し、参加選手の男女比もほぼ半々となりました。また、オリンピックの陸上競技や水泳などでは種目の男女混合化も進んでいます。柔道では女性蔑視が問題視されていた時期もありましたが、今や柔道の団体は男女混合で実施されています。今回のオリンピックの柔道で日本は金メダルを9個獲得しましたが、男女混合の団体ではフランスが優勝しました。男女協力やジェンダー平等という考え方が、フランスの力になったのではないかと思います。
このようにオリンピックでジェンダー平等が推進されていく中で、組織委員会の女性理事が少数であることは問題です。組織内での決定に女性の意見が反映されない状況は変えなければなりません。スポーツ団体の組織運営においてもジェンダー平等を目指していくことは、東京オリンピックの非常に大きな「レガシー」だと思います。
最後に、経済成長から脱成長への転換についてです。オリンピックのモットーである「より速く、より高く、より強く」は経済成長と軌を一にする価値観でしたが、こうした価値観は共感を得られなくなってきています。オリンピックが平和の祭典であるために、開催国の国民を置き去りにしないためには、「より広く、より低く、よりやさしく」という脱成長の価値観への転換が求められます。つまり、あらゆる人を包摂する「多様性」、オリンピックの開催費用を出来るだけ削減して次世代に借金を残さないという「コスト低」、そして「人権尊重」が重要となってきます。今回の東京オリンピックは、こうした「新しい価値観をもたらす黒船」だったのではないでしょうか。この「新しい価値観」という「レガシー」を日本は今後どのように受け継いでいくのか注視していきたいと思います。
ヨーコ・ゼッターランド先生(日本女子体育大学)

Twenty-Twenty~日本の未来に向けて~
皆さん、こんにちは。本日は組織委員会の理事として、選手としてオリンピックに関わる中で感じたことを交えながら、お話ししたいと思います。
東京オリンピックの開催決定後に組織委員会が発足してからまもなく、理事の1人として、お声掛けをいただきました。2020年に東京に2回目のオリンピックがやってくることは、日本の社会やスポーツ界を変えていく大きなチャンスになるという思いを持って、理事として携わってきました。
私は選手として2回オリンピックに出場しましたが、その時は支えてもらう側の立場だったわけです。私たちは整えてもらった舞台の上に立って、それまで取り組んできた成果を遺憾なく発揮しようと努めました、オリンピックで思うような結果が出なかったとしても、その辿ったプロセスというのは多くの人の夢や希望になる。だから選手の存在やその取り組む姿勢は価値のあるものだと信じてきました。
こうしたスポーツやオリンピックの価値を良いものだと信じてきた中で、コロナをはじめとする様々な問題が生じ、そして今年の2月には組織委員会の会長が交代するという前代未聞の問題が起こりました。その渦中にいた私は、自分がこれまで信じてきたことの根幹を揺さぶられました。
会長交代の問題が起こった後に、組織委員会内にジェンダー平等推進チームが発足し、ジェンダー平等をレガシーに繋げていく活動が開始されましたが、ジェンダー平等については2014年にIOCが発表した「オリンピックアジェンダ2020」で既に提言されていました。会長交代の問題が起こって初めて、ジェンダー平等に向けた取り組みが十分でなかったことが明らかになったわけです。
私がバレーボールのアメリカ代表として1996年のアトランタオリンピックに出場した時に、アメリカチームは「豊かな文化的多様性」(Rich Cultural Diversity)という見出しで新聞記事に取り上げられました。記事では、多様な人種、宗教、文化で構成されるアメリカという国家を象徴するようなチームであることが記されていますが、アメリカでは30年近く前の記事の中で既に「多様性」(Diversity)という言葉が出てきています。日本でも近年、オリンピックに出場する選手の中には、テニスの大坂なおみ、陸上競技のケンブリッジ飛鳥、バスケットボールの八村塁など、外国にもルーツを持つ選手がおり、代表選手の構成も多様化してきています。東京オリンピックの基本コンセプトの一つとして「多様性と調和」が掲げられたように、「多様性と調和」は日本の社会でも必要とされているわけです。オリンピックを「多様性と調和」を実現する一つのツールとしていくことができれば、それが東京オリンピックの「レガシー」の一つとなるのではないかと思います。

東京オリンピックのエンブレムにも記されている「2020」(Twenty-Twenty)は英語で、視力の良い人のことを指しますが、それだけでなく、視力が良いことから転じて、先見の明がある人や視野が広い人のことも意味します。「2020」年にオリンピックが東京にやってくるということの中には、日本社会が先見の明を持ってオリンピックと向き合う必要があるというメッセージが込められていたのではないでしょうか。オリンピックの開催は「2020」年から1年延期となりましたが、広い視野を持って、そして先見の明を持って日本のスポーツ界のあり方や、オリンピックを一つのツールとして社会をどのように形成していくかということを考えていかなければならないと思います。
2020東京オリンピック新体操団体 代表
熨斗谷さくら(日本女子体育大学大学院生)・竹中七海(日本女子体育大学卒業生)

~私たちを試し続けるオリンピック~
熨斗谷さくら
世界新体操選手権ではメダルを獲得してきましたが、東京五輪では経験したことがない程のミスをおかしました。夢だったら良いのにと、何度も思いました。五輪という舞台は、それまでの過程全てが正直に出る場と再確認しています。2016年リオ五輪に初出場したのち、五輪本番が重要ではなく、毎日後悔のない練習を積もうと思いました。5年間、極限の練習を乗り越えられたのは、10年近く寝食を共にしてきたフェアリーのメンバーと練習に励め、ロシア人コーチのインナ・ビストロヴァ氏、山崎浩子先生をはじめ多くの方に徹底して指導をしていただいたからだと思います。さらに、地元開催で支えてきてくれた皆さんに演技を見てもらえるという思いが、大きな原動力になっていました。一方で、「変えられるのは自分だけ」という事が信条でした。変えられない環境や他人のことなどを考えても仕方がない。メンバー全員、「今できる最善のことは何か」を考えながら過ごし、本当に全力だったと思います。歯車が狂ってしまったのは、「自分には変えられない」と諦めてしまい、「自分が変わらないから上手くいかないんだ」と、自信を持てなくなったことが原因かと思います。コロナの影響でロシア(サンクトペテルブルグ市)に行けなくなり、オリンピックが延期となり、さらに無観客となり、少しずつ心の負担が増えていきました。特に、2021年5月に行われたテストイベントでは、国内の試合に慣れていない私達には、心身が最も辛くなった時期でもありました。
五輪は、各国の力と団結が試される舞台でもあります。今後の課題は、「ピーキング」、「ジュニア世代からの強化」、「指導者の育成」だと考えています。単に全力で頑張るのではなく、その時々のベストを尽くし、心身のピークを大切にすること。ジュニア時代に、動きの基礎や試合経験を積むことで無意識化できることを増やし、シニアではこれらを応用できるようにすることが重要と感じました。このような点を伝えられる指導者を増やすことで、新体操界の層を厚くしていきたいと思います。
竹中七海
競技終了後の率直な気持ちは、熨斗谷さんと同じで悪夢かと思いました。本当に頭が真っ白で、見ていただきたい演技が踊りきれずに終わりました。悔しさと応援してくださった方々への申し訳なさが大きく、しばらくは振り返ることもできませんでした。五輪を迎える過程では、日々の練習で常に100%の出来を求めており、そうでなければ自ら落ち込んでいました。これが、疲労骨折を抱えての出場にも繋がってしまったように思います。また日常生活の何気ない瞬間にも緊張し、競技前日にはなかなか寝ることができず、極度の緊張状態でした。こういった経験から、まずは常に100%の成功だけを求めるのではなく、ピークをどの時点に持っていくのか考えながら練習すること、そして、強い自信をもって試合で踊るために、技の具体的なコツの確立と反復練習を重ね、どんな緊張状態でも体現できるようにすることが必要だと感じました。2024年のパリ五輪を目指しているので、今回思うようにできなかったことが次へのステップとなるように、最大限の準備をして臨みたいと思います。
熨斗谷さくら・竹中七海
大学を始め、応援Tシャツを着ての動画を送ってくれた新体操部の皆さん、様々な方々に応援して頂き、非常に心強く感じました。本当に、感謝申し上げます。
特に、閉会式に参加するためにバスで選手村から国立競技場に移動している際、沿道で「ありがとう」などの横断幕を持って手を振ってくれる方々が、多数いらしたことに驚きとともに、こんなにも多くの方々から応援されていたことを改めて実感しました。バスの車内で、身体が震えたことを今でも思い出します。様々なプレッシャ-やストレスなどを一人で背負い込む必要はなく、結果を残すことに囚われて、何としてでも頑張らなければ、といった自縛を解かれたような気持ちでした。

閉会式会場へ移動するバスからの沿道の風景
一方で、新体操の国際大会が国内で開催されていなかったため、ほとんどの海外選手は、初めての日本でした。彼女たちからは、「日本は美しい国だから、いつか遊びに行きたい」や「ボランティアの皆さんが、本当に親切で、優しくて、東京五輪の大切な部分だった」と話してくれました。日本人であることに、誇りを持てたような瞬間でした。今後は、世界に向けて新体操を通じて、日本の良さを発信するとともに、様々な交流を図っていきたいと思いました。日本人として東京五輪に出場できたことで、様々な側面から「国の力と団結を実感」する時間に浸ることができ、オリンピックが私達を試している意味が、僅かですが「わかった」ような気がします。これからも、この「実感できた時間」を大切にしていきたいと思います。

質問コーナー
―(溝口先生への質問)講演の中で、フランスチームは男女が協力し、男女混合の団体で活躍したというお話がありましたが、フランスは男女協力のためにどのような取り組みをしたのでしょうか。
溝口:私がフランスに滞在していた時、フランスの女子コーチは一人だけでしたが、男女平等の政治参画を促すパリテ法が2000年に制定された影響を受けて、柔道でも女子コーチが増加し、柔道連盟の役職に就く女性も増えていきました。こうした組織体制の変化がフランスの活躍を後押ししたのだと思います。
また、テディ・リネール選手が個人戦で金メダルを逃したことが大きかったです。国民的英雄である彼を手ぶらで帰国させるわけにはいかない。2012年ロンドンオリンピックの北島康介選手のような状況でした。それで、いつも以上の一体感が生まれたのだと思います。